「おっとっととっとってっていっとったとになんでとっとってくれんかったとっていっとーと」
初めて見たとき、あなたもこう思ったはずです。
「……なにこれ?呪文?」「意味が全然わからん!」
SNSや動画でこの博多弁のフレーズを見て、
- 意味が気になる
- どんな場面で使うの?
- なんで流行ってるの?
と感じて検索したのではないでしょうか?
本記事ではそんなあなたに向けて、
- このフレーズの意味や文法構造
- なぜ話題になっているのか?
- 実際のネイティブの使い方や発音のコツ
- 他にもあるおもしろ博多弁フレーズ
を、スマホでも読みやすく丁寧に解説していきます!
博多弁に少しでも興味がある方、言葉遊びが好きな方は必見です!
話題の博多弁、実はこういう意味だった!
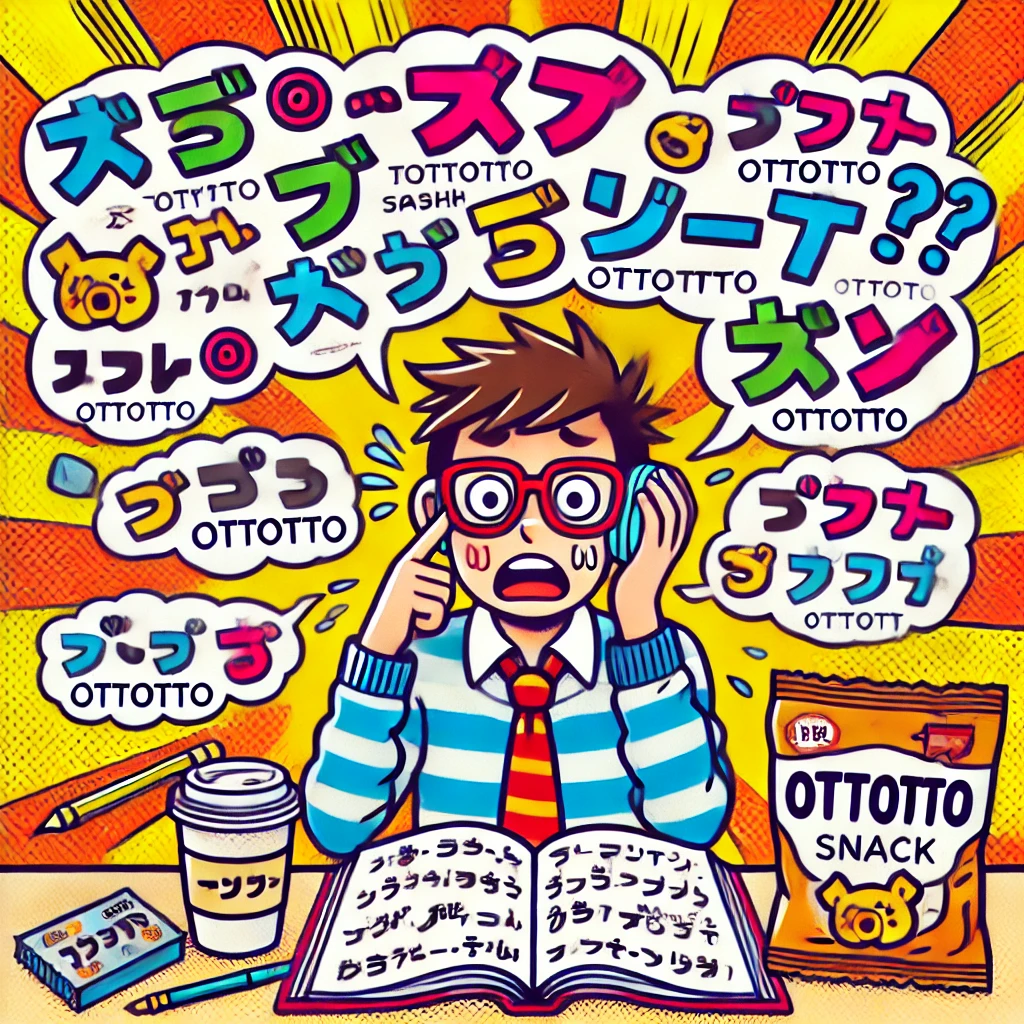
結論:このフレーズは「お菓子のおっとっと」にまつわる博多弁の早口言葉
「おっとっととっとってっていっとったとになんでとっとってくれんかったとっていっとーと」は、
博多弁ネイティブでも一瞬で理解するのが難しいと言われる、超・難解な方言フレーズです。
ざっくりと標準語に訳すと…
「おっとっと(お菓子)を取っておいてって言ってたのに、
なんで取っておいてくれなかったの?って言ってるの」
つまり、日常的なやりとりが、方言と語尾の連続によって
ものすごく複雑な響きになってしまったわけです。
なぜそんなに複雑になるの?
博多弁には特徴的な文末表現や助詞があり、
「と」や「って」が繰り返し使われる傾向があります。
以下のように分解すると、意外とシンプルに理解できます。
| 博多弁フレーズ | 標準語訳 |
|---|---|
| おっとっととっとってっていっとったと | おっとっとを取っておいてって言ってたのに |
| なんでとっとってくれんかったとって | なんで取っておいてくれなかったの?って |
| いっとーと | 言ってるのよ |
文法的にはどうなってる?
語尾の「と」「って」「とって」は、
博多弁の中では以下のように使われます。
- 「と」:断定・確認のニュアンス(例:「○○と?」=○○なの?)
- 「って」:引用や伝聞の意味(例:「〜って言った」)
- 「とって」:動詞の連用形 + 助詞の融合(例:「取って」)
これが連鎖していくことで、一見ナンセンスな呪文のように聞こえるわけです。
覚えておくと会話のネタにも!
このフレーズは、
- 方言の奥深さを知る入り口になる
- 会話のアイスブレイクやSNSネタにも使える
- 他の方言との比較ネタにもつながる
と、使いどころは意外と広めです。
ネタとしても学びとしても使える、
方言 × 言葉遊びの傑作フレーズと言えるでしょう。
なぜこのフレーズがバズったのか?
結論:SNSでの拡散と“難しすぎる方言”のギャップが人気の理由
「おっとっととっとって〜」がここまで話題になった背景には、
SNSと動画プラットフォームの影響力が大きく関係しています。
きっかけはX(旧Twitter)やTikTokでの投稿
最初のきっかけは、博多弁を紹介する投稿がバズったことでした。
- 「博多弁ネイティブでも難しい」
- 「一発で意味わかった人、すごすぎ」
- 「呪文すぎて笑った」
こうした共感と驚きの声がX(旧Twitter)で一気に拡散。
同時期にTikTokでもこのフレーズを使った“言えるかチャレンジ”動画が流行しました。
見る人を惹きつける“混乱の美学”
この言葉がバズる最大の理由は、
一見ナンセンスに見えて、実は意味があるという意外性です。
「意味がわからないけど、なんかおもしろい」
「何回聞いても頭に入ってこないのに気になる」
このように、混乱・爆笑・知的好奇心を同時に刺激されるため、
多くの人が「つい誰かに教えたくなる」「拡散したくなる」状況を生んだのです。
方言の文化としての“再発見”も一因
また、最近では地域ごとの方言が再評価される流れがあり、
- 津軽弁や鹿児島弁との比較動画
- 「この県の方言わかる?」クイズ
- 地元の言葉で伝えるシリーズ
などといったコンテンツが人気を集めています。
その中で博多弁も注目され、
このフレーズは博多弁の象徴的存在としてさらに拡散された形です。
「聞き取れないけどクセになる」
そんなギャップこそが、SNS時代の“バズる方言”の条件なのかもしれません。
博多弁ネイティブが意味を徹底解説!

結論:一語一語に博多弁ならではの文法や語感が詰まっている
このフレーズの面白さは、単に語尾が似てるだけではありません。
博多弁特有の助詞や語尾の連続性が、聞き慣れない人にとってはまるで“謎の呪文”に聞こえるのです。
一文に含まれる博多弁のポイント
このフレーズを構成する要素には、
博多弁にしかない独特な表現がいくつも含まれています。
| 表現 | 標準語の意味 | 解説 |
|---|---|---|
| おっとっと | お菓子の名前「おっとっと」 | 子どもに人気の魚型スナック |
| とっとってって | 取っておいてって | 「とっとく」=取っておく(博多弁ではよく使う) |
| いっとったと | 言ってたのに | 「〜と」=断定の語尾 |
| なんでとっとってくれんかった | なんで取っておいてくれなかったの? | 「〜くれんかった」=〜してくれなかった |
| いっとーと | 言ってるんだよ | 「〜と」=現在進行形での強調表現 |
博多弁の「と」には深い意味がある
博多弁における「と」は、
断定・疑問・強調・確認など、文脈によってさまざまな意味を持ちます。
たとえば…
- 「○○と?」 → ○○なの?(疑問)
- 「しとるとよ」 → してるんだよ(強調)
- 「見たと」 → 見たの(過去の確認)
このように、「と」が連続しても意味が変わるのが博多弁の難しさ。
それがこのフレーズを超難解に感じさせる理由の一つでもあります。
博多出身者にとっても“ネタ化”している
実はこのフレーズ、福岡県民の間でも「難しすぎるけん!」と笑いのネタにされることが多いです。
- 子どもたちが真似して遊ぶ
- 県外の人に「これ言える?」とクイズを出す
- 飲み会や授業でも使われることも
「方言って奥が深いね〜!」と再認識されるきっかけになっています。
このように、一語一語を分解して意味を把握すれば、
ただの“言葉遊び”ではなく、方言の文化そのものとしても楽しめるのが魅力です。
他の人も混乱?SNSのリアルな反応まとめ

結論:混乱・爆笑・感動が入り交じる“方言エンタメ”として大反響
このフレーズがSNSでバズった理由のひとつが、
見た人・聞いた人のリアクションが抜群に面白いことです。
実際にX(旧Twitter)やTikTok、YouTubeショートでは、
この言葉に対する多様な反応が投稿されており、話題は今も継続中です。
「???」と混乱する人が続出
投稿を見た人の最初の反応は、ほぼ間違いなくこうです。
- 「一文字目から意味わからん」
- 「最後まで読んでも理解できなかった…」
- 「これはもう博多語じゃなくて魔法だろ」
この“わからなさ”が、むしろエンタメとして機能しており、
「わからないけど笑える」コンテンツとして拡散されやすくなっています。
理解できた人のドヤ顔リアクションも話題に
一方で、意味がわかった人からは…
- 「これは博多民なら一瞬でわかる」
- 「読めるし意味もわかる!誇らしい!」
- 「通訳してって頼まれて嬉しかったw」
など、地元愛あふれるコメントやドヤ顔投稿も多数。
特に福岡出身者にとっては、
「博多弁が話題になって嬉しい!」という方言への誇りを表す声が目立ちます。
TikTokでは“言えるかチャレンジ”が人気に
TikTokではこのフレーズを実際に声に出して読む、
「博多弁チャレンジ」の動画がバズりました。
- 滑舌勝負で友達同士が大爆笑
- 家族で挑戦しておじいちゃんが神発音
- 音楽に乗せてリズミカルに読むスタイルも登場
こうした動画が拡散されることで、
言葉の面白さ × 動画映えが融合し、さらなる注目を集めています。
SNSでは「難しすぎる」が「面白すぎる」に変わる瞬間がある。
この博多弁フレーズは、まさにその代表例です。
他県の方も挑戦!音読チャレンジしてみよう

結論:言えたら盛り上がる!遊びながら博多弁の魅力を体験しよう
このフレーズは聞くだけで面白いですが、
実際に声に出して読んでみることでその魅力が倍増します。
特に他県の人にとっては、
「早口言葉」「舌噛みチャレンジ」「言語パズル」としても楽しめるネタです。
発音のコツは“リズムと区切り”
いきなり全部を一気に読むのはかなり難しいので、
まずは3パートに分けて練習してみましょう。
おっとっと・とっとってって・いっとったと
なんで・とっとって・くれんかったとって
いっとーと
このように区切ることで、リズムが取りやすくなり、
スムーズに読めるようになります。
実際にチャレンジしてみた人の声
TikTokやYouTubeでは、たくさんの人がこのチャレンジに参加しています。
- 「読めたと思ったら全然意味わからんかった」
- 「途中で噛んで爆笑」
- 「博多弁ってこんなにテンポ良かったんだ!」
友達や家族で挑戦して、
笑いながら方言を学ぶ時間になるという声も多いです。
自分でも投稿してみよう!
もしうまく言えたら、
ぜひその様子をSNSに投稿してみましょう。
おすすめのタグはこんな感じ:
- #博多弁チャレンジ
- #おっとっと早口
- #言えるかな選手権
動画や音声付きの投稿なら、再生される可能性もぐんと高まります!
「方言は難しい」ではなく「方言は面白い」に変えていこう。
博多弁の魅力を、あなたの声で届けてみてください。
他にもある!おもしろ博多弁フレーズ集
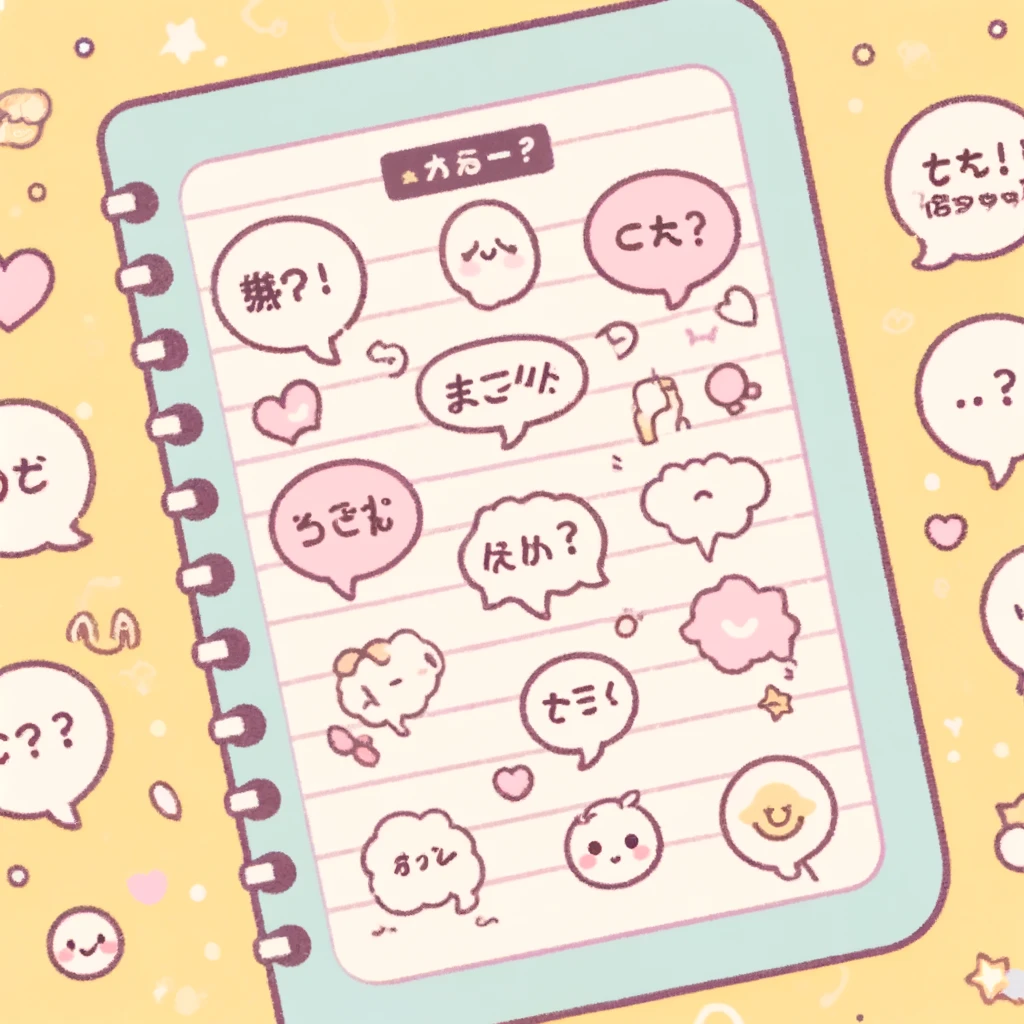
結論:博多弁はリズムと言い回しが独特で、他にも“ネタになる”表現がいっぱい!
今回話題になったフレーズ以外にも、
博多弁にはおもしろい・使ってみたくなる言い回しがたくさん存在します。
ここではSNSや地元トークで話題になりやすい、
笑えて覚えやすい博多弁フレーズをいくつか紹介します。
1. なんばしよっと?
意味:何してるの?
標準語で言うと普通ですが、博多弁にするとグッとフレンドリーな印象に。
使い方:「あんた、なんばしよっと〜?」
2. 好いとーよ
意味:好きだよ
博多弁の恋愛フレーズといえばこれ。やわらかい語感で人気。
例:「○○のこと、好いとーよ(照)」
3. てれてれしよるね〜
意味:ニヤニヤしてるね〜、照れてるね〜
ちょっとからかい気味に使う表現。語感がかわいくて人気です。
例:「ほら〜てれてれしよるやん!」
4. よかよか
意味:いいよ・大丈夫よ
やさしい響きで、親しみが伝わる言い回し。
例:「そげん気にせんでよかよ〜」
5. しゃーしか!
意味:うるさい!(ちょっと怒ってる)
感情がダイレクトに伝わる言葉。場面によっては注意が必要かも?
例:「あーもう、しゃーしか!」
ちょっとした“語尾のクセ”もポイント
博多弁は「〜と?」「〜ばい」「〜っちゃ」など、
語尾に特徴が出るのも魅力のひとつ。
例:
- ほんとにそうなん? → ほんとと?
- 行くよ! → 行くばい!
- それやけん! → それたい!
博多弁はただの方言じゃない。
親しみ・リズム・人情が詰まった、愛される“ことば”なんです。
博多弁の魅力と奥深さ

結論:博多弁は“あたたかさ”と“リズム感”がある、全国に誇れる方言
「おっとっととっとって〜」のような難解な言い回しに注目が集まりましたが、
実は博多弁の魅力はそれだけではありません。
博多弁には、感情をダイレクトに伝える力と、
相手との距離を縮めるやさしさがあります。
リズムで伝わる“心の距離感”
博多弁はテンポや語感がとても独特で、
どこかメロディカルな響きがあります。
- 「なんしよーと?」
- 「そげん言わんでもよかろーもん」
- 「あんた、よか人やね〜」
こうした言葉には、怒りや喜びさえも“やさしく”伝える不思議な力があります。
人とのつながりが深まる方言
博多弁を使うことで、
会話が一気にフランクになったり、
心の壁がスッと下がる瞬間があります。
例えば:
- 親しい相手に「好いとーよ」って言われると、標準語より何倍も嬉しい
- 初対面でも「なんばしよっと?」と声をかけられると一気に和む
こうした“人懐っこさ”や“親しみやすさ”が、
他の方言にはない博多弁の魅力です。
文化としての価値も再認識されている
近年、地元の方言や言葉を守ろうという動きも広がっており、
博多弁もその流れの中で地域のアイデンティティとして再評価されています。
- 地元ラジオやテレビ番組での使用
- 方言を生かしたキャッチコピーや観光PR
- 小学校やイベントでの「方言講座」
ただの方言ではなく、“福岡の文化そのもの”として誇れる存在になっているのです。
博多弁は“話す人の心”を映す鏡
難しい言い回しも、やさしい語尾も、
すべてが人との関係性を大事にする博多の気質を映し出しています。
「おっとっと〜」のフレーズに笑ったあなたも、
きっとその奥にあることばの温もりを感じ取っているはずです。
まとめ
SNSで話題となった
「おっとっととっとってっていっとったとになんでとっとってくれんかったとっていっとーと」
というフレーズは、単なるネタではありません。
- 博多弁の構造やリズムの面白さ
- 地域文化としての深さや温かさ
- SNS時代にぴったりな“混乱×共感”の要素
がすべて詰まった、まさに言葉のエンタメです。
この記事でわかったこと
- フレーズの意味は意外とシンプルで日常的
- 博多弁の「と」「って」が混ざることで難解化
- SNSやTikTokで拡散され、リアクションも多彩
- 実際に読むとさらに面白い!
- 博多弁には他にも魅力的な言い回しが多数存在
- 方言には人との距離を縮める力がある
言葉って、知るともっと面白い。
そして、話してみるともっと好きになる。
ぜひあなたも、
誰かにこのフレーズを紹介して、
一緒に笑って、噛んで、楽しんでくださいね!
参考リンク
以下は、本記事作成にあたり参考にした情報源や、さらに詳しく知りたい方へのおすすめリンクです。
- BuzzFeed Japan|博多弁の難解フレーズが話題に
- Yahoo!ニュース|博多弁「おっとっと〜」が話題に
- TikTok|#博多弁チャレンジ 検索結果
- 方言マップ|全国の方言一覧と比較
- YouTube|「博多弁フレーズを言えるか?」チャレンジ動画集
※一部リンクは外部サイトに遷移します。閲覧時は各サービスの利用規約をご確認ください。


